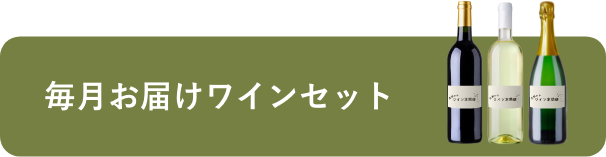こんにちは!業務部の中谷です。去る2月、マールボロの独創的な作り手「フォリウム・ヴィンヤード」を訪問してきました。


■フォリウム・ヴィンヤード
ニュージーランド・マールボロ地方。南島の北端に広がるこの地は、豊かな日照と涼しい海風に恵まれ、世界でも有数のソーヴィニヨン・ブランの産地として知られています。
その中心地に、静かに、しかし確かな個性を放つワインを造り続けている造り手がいます。「フォリウム・ヴィンヤード」岡田岳樹氏。今回は、そんな岡田さんの畑を訪ね、直接話を伺うという貴重な体験をしました。
自然と向き合いながら、芯のある哲学で造る岡田さんが所有する畑の面積6ヘクタール。その規模から想像される以上に、そこには深い哲学が詰まっていました。特に印象的だったのは、産地の個性に拘らない自然に寄り添うアプローチです。
ピノ・ノワールには灌漑を一切行わず、ソーヴィニヨン・ブランにおいても2016年を除いて灌漑はしていません。「ソーヴィニヨン・ブランは本来、水が必要な品種なんですけどね」と笑いながら話す岡田さん。しかしそこには明確な意図がありました。
「灌漑を控えることで、いわゆる“ニュージーランドらしい”チオール香(パッションフルーツや青臭さ)が抑えられる。結果として、どこのワインか分からないくらい“ニュートラル”な香りになるんです。でもそれでいい。ワインとしての完成度を高めたいから。」
この言葉には、土地の個性に頼るのではなく、ヴィンテージの個性や、自分のスタイルで勝負する覚悟がにじんでいました。
【栽培哲学:敢えて灌漑しない意味】
マールボローでは灌漑はごく一般的であり、特にソーヴィニヨン・ブランにおいては、果実のフレッシュなアロマを得るための手段として定着しています。でも岡田さんは、ピノ・ノワールに関しては一切灌漑を行っておらず、ソーヴィニヨン・ブランについても2016年を除き、完全なドライファーミングを実践。
このスタイルの背景には、「ヴィンテージを正直に表現したい」という岡田さんの信念があるとの事。
灌漑によるストレス緩和は、確かに果実の均一性を高めるが、その反面、年ごとの差異を平準化してしまう。ヴィンテージのばらつきをネガティブに捉えるのではなく、むしろ楽しみとして取り入れてるそうです。
特にマールボローのように日照量が安定している地域においては、果実の表現力はむしろ水分ストレスにより高まると考えています。



ティスティング① バレルから
■ ソーヴィニョン・ブラン 2024
まだ発酵のニュアンスが残る中にも、白い花やグリーンアスラ、ライムのような清涼感のある香りがそっと立ち上がります。口に含むと、ピュアで澄んだ酸が真っすぐに流れ、余計な装飾を排した透明な構成。現段階ではチオール的な主張は抑えられていました。
■ シャルドネ 2024
控えめながら白桃、アーモンドの皮、仄かにレモンピールの香り。まだタンクらしい“若さ”を感じるものの、ミネラルの骨組みが既に見えており、芯のあるエレガンスを予感させます。
■ピノノワール 2024 2種(石灰質土壌と粘土質土壌)
石灰質土壌は赤スグリや若いチェリーのような、やや硬質な赤果実香が中心。タンニンはまだ粗く、果実味も引き締まっていますが、ミネラル感とスパイスの気配に、石灰質由来の緊張感がはっきりと現れています。
粘土室土壌は熟したラズベリーやプラム、ほんのりスミレの香り。タンニンはまだ若く未熟ながらも、丸みを帯びた印象で、ふくよかさと包容力のあるスタイルに仕上がりそうです。石灰質土壌のサンプルが“縦の構成”だとすれば、こちらは“横の広がり”が感じられる対比的な味わいといえます。

ティスティング②
■ ソーヴィニョン・ブラン リゼルヴァ 2018
収穫から時間が経ったことで、若い頃の瑞々しさは穏やかに後退し、代わりに落ち着きと深みが加わった印象。パッションフルーツやハーブの香りは控えめになり、蜜柑の皮やドライハーブ、仄かな燻香を感じました。
■ ソーヴィニョン・ブラン リゼルヴァ 2017(ラベル無)
17年よりも果実の存在感があり、グレープフルーツや白桃、ほのかにグアバを思わせる香り。ミネラルと冷涼感のある酸が芯に通っており、凛とした佇まいを保っています。チオール香はほとんど感じられず、マールボローらしさを敢えて引き算で表現したような印象。
■ピノノワール リゼルヴァ 2021
21年というまだ若いヴィンテージながら、既に香り立ちは非常に複雑。赤い果実(ラズベリー、チェリー)に加え、シナモン、ドライローズ、ニューワールドのピノらしくはない土や葉のニュアンスも感じました。
味わいはまだ若々しさがあり、タンニンも瑞々しくエッジが立っていますが、その下には将来的な美しい熟成を予感させる静かな重心が感じられます。灌漑を行わないフォリウムの哲学が、果実の自然な力強さとして表現されており、今飲んでも良し、熟成を待つもまた楽しめるワインといえます。
近年のヴィンテージに関して 岡田さんから聞きました。
| 2017年 | 生育時に乾燥して、開花期と収穫期に雨が多く降りました。 多くの生産者は収量が減少しましたが、周りの状況見て奇跡的なタイミングで 収穫できたのでフォリウムでは大きな減産はなかった。 |
| 2018年 | 温暖で乾燥した気候が続き、夏は雨が多かったけど意外にもブドウは順調に成熟しました。 収穫量も多く、全体的にバランスの取れたワインが生産されました。 |
| 2019年 | この年は良好な天候に恵まれ、特にピノ・ノワールには特に良い乾燥した年。 昼夜の寒暖差が大きく、酸と果実味のバランスが優れたワインが生まれました。 |
| 2020年 | どんな年とかというよりも、コロナの影響がおおきかった。 地味な表現ですけど、普通の年?ピノ・ノワールには良かった乾燥した年だった。 |
| 2021年 | 温暖な気候が続き、ブドウは順調に成熟しました。 穏やかで乾燥したフルーツ全面のような感じではなく凝縮した個人的には良い年。 |
| 2022年 | 開花期の天候不順により収量が大幅に減少。特にマールボローは例年の50%程度の収量。 甘口を作らざるえなかった年。結果、甘口は2022年特有なので良かった。 |
| 2023年 | 前半は一言で普通。ホークスベイで収穫期に降雨があったけど、 この年も情報の速さで非常に助かった年。特にシャルドネはいい仕上がり。 |
| 2024年 | 乾燥した暖かい気候が続き、収穫期には気温が下がって理想的にゆっくりと成熟が進んだ。 凝縮感とバランスの取れたワインができると期待しています。 |
岡田さんが言うには最高の年という概念は持っていないそうです。平凡な年こそ、良い年といえるのではないかと仰ってました。
数値よりも、舌と感覚を信じてワインを紹介いただく中で、岡田さんが何度も語っていたのが「感覚」の大切さでした。
「糖度計や酸度計はもちろん使うときもあります。でも、結局は自分の舌が一番信用できるんです。」
果実の香り、果皮の張り、種の色――。数値では表せない微妙な変化を五感で感じ取りながら収穫のタイミングを見極める。その姿勢は、哲学者的なコメントして、まさに職人気質も感じました。私自身も、畑の空気や土の匂い、現地の空気感に心が動かされ、「ワインは畑で決まる」という言葉の本当の意味を実感した瞬間でした。
環境へのまなざし ― ペットボトル論と未来のワイン像岡田さんは、サステナビリティについても聞いてみました。特に印象深かったのが、ワインボトルの在り方についての発言です。
「ワイン産業のCO₂排出量の3〜4割は、瓶の製造から来ているんです。本当に環境のことを考えるなら、ペットボトルに変えるべきだと僕は思ってます。」
この一言には驚かされましたが、話を聞いて納得しました。アメリカでは、スーパーマーケットで買われたワインの9割が、購入後48時間以内に抜栓されているというデータもあるそうです。
「熟成を目的としないデイリーワインなら、軽くて環境にも優しい素材を選ぶ方が合理的。全部じゃなくていい。選択肢のひとつとして、ちゃんと議論されるべきだと思うんです。」
伝統へのリスペクトを忘れずに、未来の飲み手や地球環境まで見据えた言葉に、ワイン専門職としてのキャリアもある自分自身もつい納得してしまいました。
■温暖化にどう向き合うか
気候変動について温暖化に関しても聞いてみました。岡田さんは独特でありながら、明確な視点を持っていました。
「まずはブルゴーニュが先に影響を受けると思うんです。そのとき、生産者がどんな選択をするのか。それを見てから、自分の方向性をじっくり定めたい。」
あえて急がない。時間をかけて自然や世界の動きを観察し、自分なりの答えを探す――その姿勢には、焦らず誠実に「本物」を追求する岡田さんらしさがにじんでいました。
■学び、考え続ける姿勢
2023年にはポール・ピヨ氏の息子さん、2024年にはシャブリの名門ラヴノー氏の息子さんが研修に来るなど、世界中の若き才能たちの学びの場にもなっています。
多くの生産者からも注目を集め始め、新しい切り口の考えを持つこのような方が未来を切り拓くのだと強く感じました。
フォリウム・ヴィンヤードを訪れた日は、穏やかな風が畑を撫で、ぶどうの葉がさらさらと音を立てていました。
その中で語られる岡田さんの言葉の一つひとつは、理屈やデータを超えた、現場の重みと温もりに満ちていました。「シンプルなレシピの中で、ヴィンテージごとの個性を楽しむ。それが一番面白いんです」と語る岡田さん。
その姿から、ワイン造りの本質、そしてこれからのワインの在り方について、多くのヒントを得ることができました。“マールボロの異端者”と呼ばれ、それを前向きに受け止める岡田さん。それは、誰とも競わず、ただ真摯に、自分の美意識と自然の声に耳を傾け続けているからなのかもしれません。


#ワイングロッサリー #京都ワインショップ #京都 #ワイン #kyotowine #winegrocery
#ニュージーランドワイン #フォリウム・ヴィンヤード